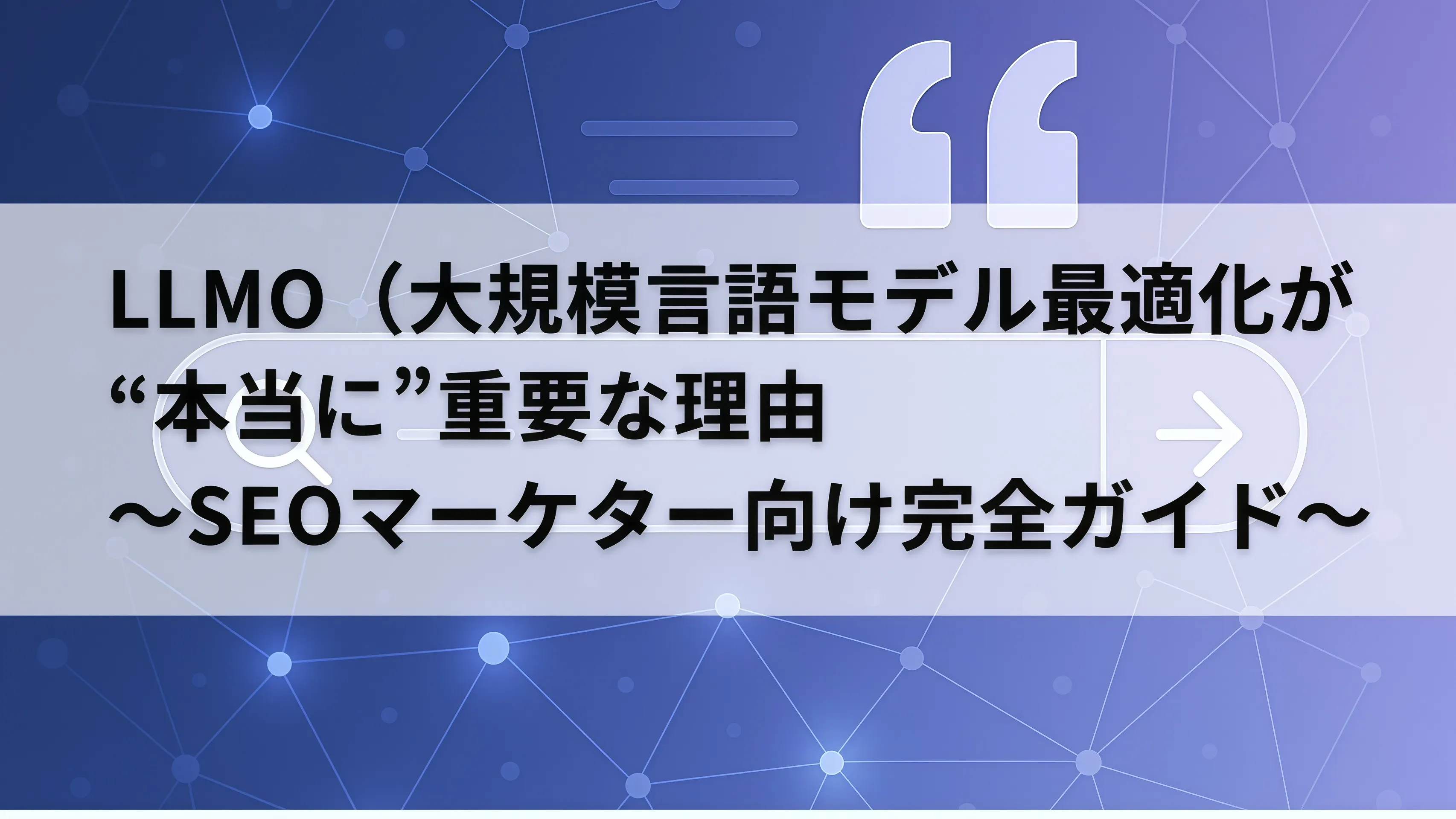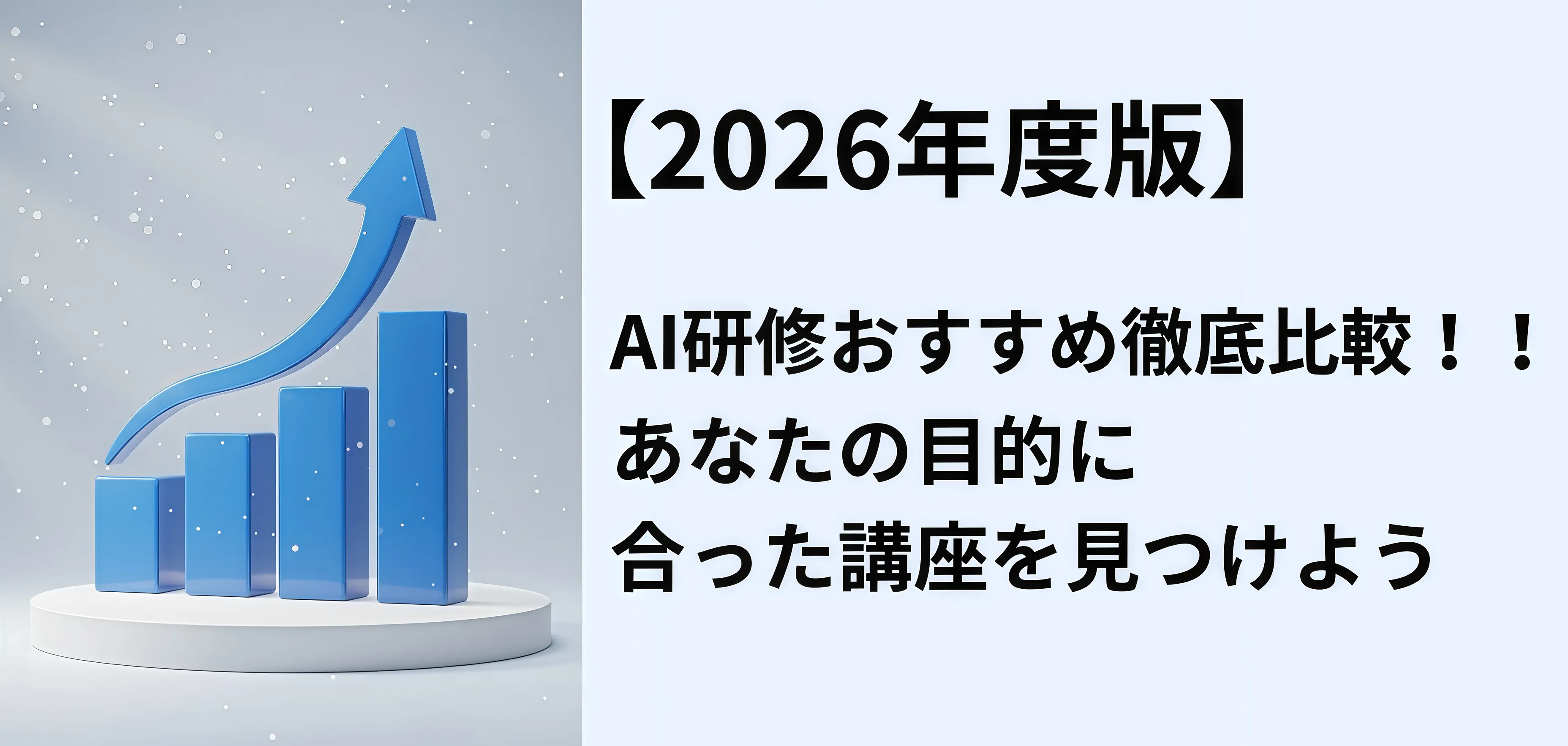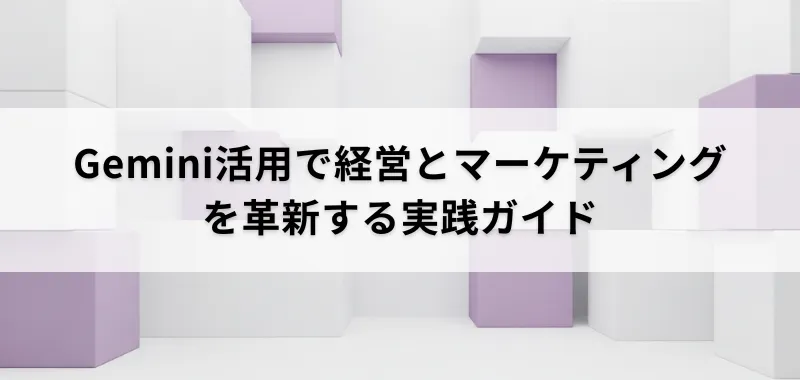1. はじめに:なぜSEOだけでは足りないのか
多くのサイト運営者が「検索順位1位を取れば流入は安定する」と信じてきました。しかし、近年登場したAI要約(AI Overviews)は、検索結果画面上に要点を直接表示することで、上位表示されてもクリックされない状況を生み出しています。
実際、Ahrefsの分析では、AI Overviewsが出現するクエリでは1位のCTR(クリック率)が約34.5%低下したとの報告があります。(出典:Ahrefs)
また、Search Engine Landも、AI Overviewsによりオーガニック流入が損なわれるケースを多数指摘しています。
このような変化を前に、SEO(検索エンジン最適化)だけに依存する戦略はリスクを伴う時代になりつつあるのです。
2. LLMOとは?SEOとの違いを整理する
LLMO(Large Language Model Optimization)の定義
- LLMOとは、ChatGPTやGemini、Googleの生成AIなどが回答を生成する際に、自社のコンテンツを根拠・引用先として選ばれやすくするための最適化施策群を指します。
- 別称で GEO(Generative Engine Optimization) や AIO(AI Optimization) と呼ばれる場合もあります。
SEO と LLMO の主な違い(比較)
| 観点 | SEO最適化 | LLMO最適化 |
|---|---|---|
| 主な対象 | Google/Bing などの検索エンジン | 大規模言語モデル(生成AI) |
| KPI | 検索順位、オーガニック流入 | AI回答での引用・言及率、AI検索チャネルからの流入 |
| 最適化の手法 | キーワード、内部リンク、被リンク | 論理構造・根拠明示、著者信頼性、要約文整備 |
| 資産 | ページ・記事 | ブランドとしての根拠群(実績、データ、著者保証など) |
「検索に強い=AIに強い」とは限らない時代に、SEOを下地に据えながらAI向け設計を追加するのが現実的な戦略と言えます。
3. なぜ「今」LLMOをやるべきか? — 5つの理由
1. AI要約によるクリック減少リスクの回避
前述のCTR低下傾向は、単なる仮説ではなく多くのクエリで観測されています。AI要約が出ると、上位でもクリックが奪われやすくなるため、従来SEOだけでは流入を確保できない局面が出てきています。
2. ユーザーが“AIに直接質問する”体験が増えている
検索ではなく ChatGPT に聞く、AIに相談する という行動をとる人が増えています。生成AIは前処理的な調査や知識確認の場としても使われ、最初の接点としてAI回答が使われる機会が拡大中です。
3. AI回答に“引用される”価値が生まれる
AIが回答文中で自社のWebページやブランド名を根拠・引用として使うと、流入だけでなくブランド想起・信頼性の強化にもつながります。
4. 競争優位を作れるフェーズ
LLMOはまだベストプラクティスが定まっていない領域のため、早めに取り組むことで他社に先行できる可能性があります。
5. SEOを否定せず補完できる
LLMOはSEOを否定するものではなく、SEOを基盤とした“AI世代対応の拡張”とみなすべきです。
4. SEOマーケターが理解しておくべき LLMO 設計の“5つの土台”
1. E-E-A-Tを“AIにも解釈しやすく”明文化する
- 著者情報・監修者情報・実績・信頼できる一次データ・出典元を、文章中で明示する
- 表組・引用ブロック・脚注的記載など、情報の構造化でAIが読み取りやすく
2. 段落構造を“問い → 要約 → 根拠 → 詳細”型に整える
AIは冒頭要約や見出しから情報を抜き出しやすいため、結論を最初に示す形式が有効です。
3. 固有名詞・数値・日付を具体的に記載する
- 「2025年10月13日」などの絶対日付を明記
- 製品名・企業名・担当部門名など固有名詞を入れる
- 出典・出どころを明示(例:「Ahrefs分析 2025年3月」など)
4. 一次情報・オリジナルデータを盛り込む
- アンケート調査・社内ログ・図表・スクリーンショットなど
- 手順や実体験を自社事例で提示
5. 外部露出を増やし、AI学習対象になる機会を持つ
- 技術フォーラム・Q&Aサイト・登壇資料・論文などで“検証ログ・方法論”を公開
- 他サイトの引用/サイテーションを得に行く
5. 実践ロードマップ(90日プラン)
0〜2週:現状観測とベンチマーク
- 「自社名 + 主テーマ」で ChatGPT / Gemini に質問しAI回答例を取得・保存
- 回答中の自社言及・出典URL・文脈位置を整理
- 競合でも同様の質問をして差分を把握
3〜6週:コンテンツ構造の再設計
- 主要ページの見出し・導入・結論文を前倒しで定義
- 著者情報・監修体制・実績・出典を適切に挿入
- 要約文(3〜4文)を冒頭に置くバージョンも用意
7〜10週:一次データ・差別化資産構築
- 小規模アンケート・ユーザー調査・実測データを作成・公開
- 図表やスクリーンショットを挿入
- 結果の解釈・分析プロセスもオープンに記載
11〜13週:観測→微調整→拡張
- 同一プロンプトで定期的にAI回答を取得し変化を追う
- 自社名・URL出現頻度のトレンドをモニタ
- AI要約がよく出るクエリには“要約バージョン”を準備
6. よくある疑問と実務的回答
Q1:AIは必ず出典を載せるのか?
A:いいえ、必ずではありません。 プロダクトや文脈に依存。出典を示さない場合も多いため、「引用される可能性を高める設計」を目指します。
Q2:SEOをやめてLLMOに全部移すべきか?
A:いいえ。 「SEO + LLMO拡張」が現実的な道です。
Q3:LLMOの効果はどう測る?
A:代理KPIで傾向を捉えます。
- AI回答における自社名 / URL 出現率
- ブランド指名検索数の推移
- 被リンク・引用の増加
- 問い合わせ時の“AI経由”自己申告
Q4:どんなテーマでAI要約が出やすい?
一般に「what/how 型」「比較型」「手順型」などで出やすい傾向。ただし日本語・テーマ依存性が大きく、すべてで必ず出るわけではありません。
7. まとめ:SEO時代からAI時代への移行を乗り越える鍵
SEOは依然大事ですが、「AI に引用されるかどうか」がAI時代の新しい勝ち筋になります。完璧な最適化手法は未確立だからこそ、観測・仮説検証型運用が重要です。ブランドとしての根拠群を整えつつ、SEO資産をベースにAI最適化を追加していきましょう。
8. サービスご紹介:LLMO Insight(LLMO インサイト)
AI検索における自社・競合の“見られ方”を、定量・可視化できるのが LLMO Insight です。
“ChatGPTで自社がどう扱われているか”をデータで捉えたい方に
AI回答文中での自社言及頻度・競合との並び・引用文脈を定点観測し、改善施策を導くレポーティングサービスです。
LLMO Insightの詳細を見る